日曜の記事で書いた“怖い話”。
無職のはずなのに介護保険料の納付書が届いた――64歳の姉さんの体験談でした。
私も最初は「え?どうして?」と混乱しましたが、調べてみると正体は意外とシンプル。
ただし呼び方のトリックで、とても“ややこしや~”だったのです。
年金と介護保険の「第1号・第2号」は別モノでした
混乱の大きな原因はここ。
年金と介護保険で「第1号」「第2号」という呼び方が同じなのに、中身がまるで違う のです。
【年金の区分】
- 第1号=自営業・無職
- 第2号=会社員
- 第3号=会社員の配偶者(扶養)
【介護保険の区分】
- 第1号=65歳以上
- 第2号=40〜64歳
呼び方は同じでも別モノ。
これが“スパゲティコード”の正体でした。
64歳で納付書が届いた理由
姉さんご夫婦はともに国民健康保険に加入。
国保では原則「世帯主が世帯員全員分をまとめて」保険料を支払います。
ところが、65歳になると介護保険は【第1号被保険者】に切り替わり、
それぞれ本人ごとに納付する仕組み に変わります。
ただし、年金からの天引き(特別徴収)が始まるのは65歳から。
その直前の64歳には、 準備期間として一旦“納付書”が送られてくる のです。
つまり「間違いではないけれど、知らなければ怖い」――これが正体でした。
働きたくても働けなかった私たち世代
姉さんは「私はまだ第3号だから夫が払っているはず」と思っていました。
でも実際には、ご主人が退職した時点で第3号から外れて国保に切り替わっていたのです。
思い返すと、私たち世代にはこんな“あるある”があります。
当時、保育料はとても高くて、とてもじゃないけど子どもを預けて働くことはできませんでした。
「働かない」ではなく「働けなかった」――これが現実だったんです。
それでも家庭を支え、子どもを育て、地域の役割も担ってきました。
“働いていない”なんて、口で言われるほどヒマじゃなかったんです。
第3号も途中からできた制度でした
思えば、第3号被保険者の制度自体も、私たちが子育てしていた頃に始まったものでした。
熊谷真美さんが「サラリーマンの奥さん届」と言いながら土手を自転車で走るCM、覚えていませんか?
あのCMを見て「これで私たちも年金に入れるんだ」とホッとしたのを、今でも憶えています。
最初からあった制度じゃなく、途中でできた仕組みだったんですよね。
自己責任と言われてしまう切なさ
それなのに今では、第3号で守られてきたことを「甘え」や「自己責任」と言われてしまう。
年金が少ないのは自分の選択のせいだ、と片づけられる。
60歳になれば夫の退職金でフルムーン旅行。
そう信じて頑張ってきたのに、現実は定年は延び、届いたのは介護保険料の納付書。
これは、同世代ならきっと「そうそう!」と頷いてくださるのではないでしょうか。
まとめ
怖い納付書の正体は「65歳からの天引きに向けた準備」でした。
知っていれば慌てずにすむし、今からでも少しずつ備えることができます。
怖さは消えないけれど、正体がわかれば落ち着けます。
姉さんに感謝しながら――
それでは今日はこの辺で。
ごきげんよう!


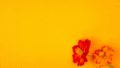
コメント